- 2025.02.27
「Staff Stories」では、モンスターラボのスタッフを紹介しています。今回登場するのは、ビジネスデザイナーの友部仁傑。モンスターラボでは大阪拠点やビジネスデザインチームの立ち上げなど、組織の改革をリードする存在として活躍してきました。そんな友部の背景や今後の展望について聞きました。
Guest

-
Hirotaka Tomobe
2007年より定性調査に強みを持つデザインコンサルティング会社のコンサルタント / プ ロデューサーとして大小様々なプロジェクトの立ち上げ・運営支援に従事。 B2Bを中心に多種多様な業界・クライアントと各種調査の実行から企画の立ち上げ、運営までを支援。 2015年よりモンスターラボ 大阪拠点責任者としてジョイン。モンスターラボのデジタル領域の開発力をベースにビジネス・UXデザインを起点とした新事業・サービスの戦略策定支援や企画立案、仮説検証の他、クライアントの既存ビジネスのグローバル展開支援など様々なタイプのDXプロジェクトに参画の上、伴走支援している。
美術大学受験の過程で育んだ「本質」と「課題」への向き合い方
— まずは友部さんのこれまでについてお伺いします。学生時代はどのように過ごされていたのでしょうか?
絵を描くのが好きで美術大学への進学を考えていたのですが、両親の反対もあって一般の大学を受験しました。ただ、モチベーションがあがらなくて勉強も進まず、すべて落ちてしまったんです。この先どうするか考えた結果、「どうせ失敗するなら、やりたいことをやって失敗したい」と思い至り、住み込みで新聞配達のアルバイトをしながら稼いだお金で美術大学の予備校に通うことにしました。人に比べて遅いと思うのですが、高校を出て、家も出た(追い出された?)ことではじめて、人としての自立が始まったと思います。
はじめは「すぐに合格するぞ」と意気込んでいたのですが、結果的にその予備校に3年通いました。なぜなら、素敵な先生と出会い、その先生のもとで学んだ方がためになると思ったからです。その先生は受験のテクニックには一切触れず、ものの見方や本質の捉え方を徹底的に教えてくれる方でした。
— その後、美術大学には進学されたのでしょうか?
3年経った頃に先生に「君、さすがにもういいでしょう」と言われ(笑)、受験を経て、京都芸術大学の空間デザイン学科に入学しました。3年の間に絵を描くことではなく本質を捉えることに重きを置くようになっていたこと、そして、年月を越えて普遍的に残りつづけるものにも興味があったため、長い歴史を持つ京都の地で学んでみたいと考えての選択です。それに、絵だけで食べていく難しさもわかっていたので、食べていける仕事としてデザインを学びたいとも考えました。
ちなみに、入学後に急遽空間デザイン学科の学長が代わり、新設されたイベントプロデュースコースで新しく学長として入られたアーティストの方のもとで学ぶことになりました。「新しいコトを興す」という点では今の僕のテーマと通じる部分でもあり、ここでの学びや経験も今の僕の基礎に繋がっていると思います。
— 入学後は、どのようなことを学びましたか?
大学で得た気づきの一つが、「アウトプットの良し悪しは、課題の良し悪しに左右される」ということです。そもそも何を課題に設定するかにこそ、デザインの本質があるのだと感じるようになりました。卒業後も課題設定から関わることのできる会社に行こうと考え、新卒ではデザインコンサル会社に入社しました。
「質より量」人の3倍の仕事をこなして得たブレイクスルー
— デザインコンサル会社では、どのような経験をされたのでしょうか?
やる気はありましたし、課題を疑い新たに設定することはできたものの、クライアントのやりたいことをきちんと考慮できず、はじめの4年間はコンサルタントとして鳴かず飛ばずでした。そんな状態だったので役員命令のもと、コンサルティングの考え方や営業力を徹底的に強化する研修を受けることになったんです。約1年に渡り研修を受けた結果、他のメンバーの3倍の実績を出せるまでになりました。
研修を通じて得た最も大きな学びは、「量に勝る質はない」ということです。量を圧倒的にこなすことを叩き込まれ、文字通り3倍の量をこなしたことで、提案資料をつくらずとも受注できる状態にまで持っていくことができました。
もしかしたら、単にそれまでの僕のやり方が間違っていたのかもしれません。クライアントのやりたいことを捉えつつ、僕たちが良いと思う正解へつなげていくには、そもそももっと量をこなさなければその本質など見えるわけがなかったのだと思います。
— そもそも、なぜ質より量が大切なのでしょうか?
量をこなすことで一つひとつの課題や解決策の中から普遍性のあるパターンを見つけることができ、そのパターンを組み合わせることで、更に広く、多くの課題解決が出来るようになるのだと考えています。持っているパターンの数が多ければ多いほど、大きな問題を素早く解決できるようになりますし、解決の質もあげることができるのかなと。
この「質より量」の考えは、今でも自分の中に生きています。モンスターラボに転職してすぐの頃はデジタルプロダクト開発やその開発プロジェクトの立ち上げの経験もなかったので、あり得ないくらいの量をこなすことに注力しました。とにかく必死でしたが、前職では量をこなすことで一定の成果を出すことができたので、同じように成果を出せると信じていました。
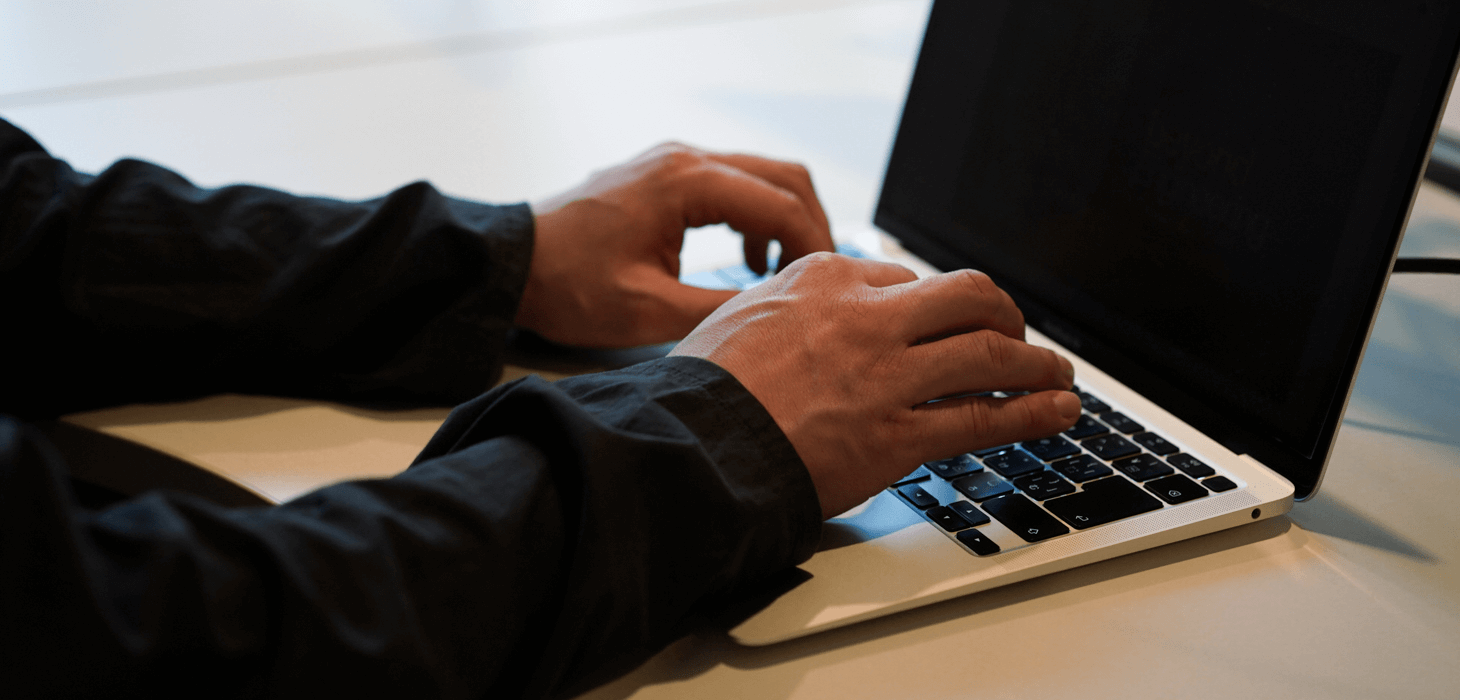
世界に通用するプロダクトづくりを。モンスターラボ大阪拠点の立ち上げ
— モンスターラボに入社後は、どのような業務に取り組んできましたか?
モンスターラボへは大阪拠点長として入社し、拠点の立ち上げとして人材採用から案件獲得まで幅広く取り組みました。
入社時のキーワードは「デジタル」と「グローバル」です。前者に関しては、当時すでに関西のものづくり企業はハードウェアだけでは成長できなくなってきていたため、デジタルの力をかけ合わせて新たな事業成長力の創出支援を目指していました。
後者に関しては、人口が減少傾向にある日本の内需向けだけでなくグローバルの外需向けで勝負できるものをつくり、さらなる成長支援につなげていきたいという狙いがありました。その可能性を秘めたプロダクトを持つお客様に対しては、積極的に声をかけたり、自らプロデューサーとして手をあげることを意識していました。
ちなみに、私の中では「グローバル」は「全世界共通の普遍性」を意味し、各国ごとに最適化してローカライズするアプローチは「インターナショナル」と定義し、区別して捉えています。インターナショナルのアプローチは、バブル期の日本だけが突出していた時代の取り組みだと思っており、現代には通用しにくいものと考えてます。現在は各国の現地企業が同様の事業展開ができる時代ですので、地域に根ざした小さく、早く、安く展開できる企業が競合になり、苦しい戦いを強いられます。よって、僕はグローバルに展開していけるiPhoneのようなプロダクト開発と事業展開支援を目指しています。
これまでグローバルなプロダクト開発・展開を支援するプロジェクトのプロデュースにいくつか挑戦してきて、正直まだ思うような成果は上げられていませんが、まだ諦めていません。モンスターラボが持つ可能性を活かしたグローバルなプロダクト開発と事業展開支援を成功させたいという思いこそが、現在も僕がモンスターラボに居続けている理由と言えるかもしれません。
— グローバルでの成功のために、どのようなポイントを大切にされていますか?
人間の普遍的で本質的な欲求や行動に沿ったものこそ、時間を越え、国を越える可能性を秘めていると考えています。たとえば、過去に映像配信者のプラットフォーム開発支援プロジェクトに関わっていたのですが、「自分を見てもらいたい」という欲求は全世界共通のものですよね。そういった人々の秘めたる欲求を束ねるグローバルプラットフォーム上で、日本が強みを発揮できるコンテンツを全世界に提供出来るビジネスには、可能性を感じており、その見極めを大切にしています。
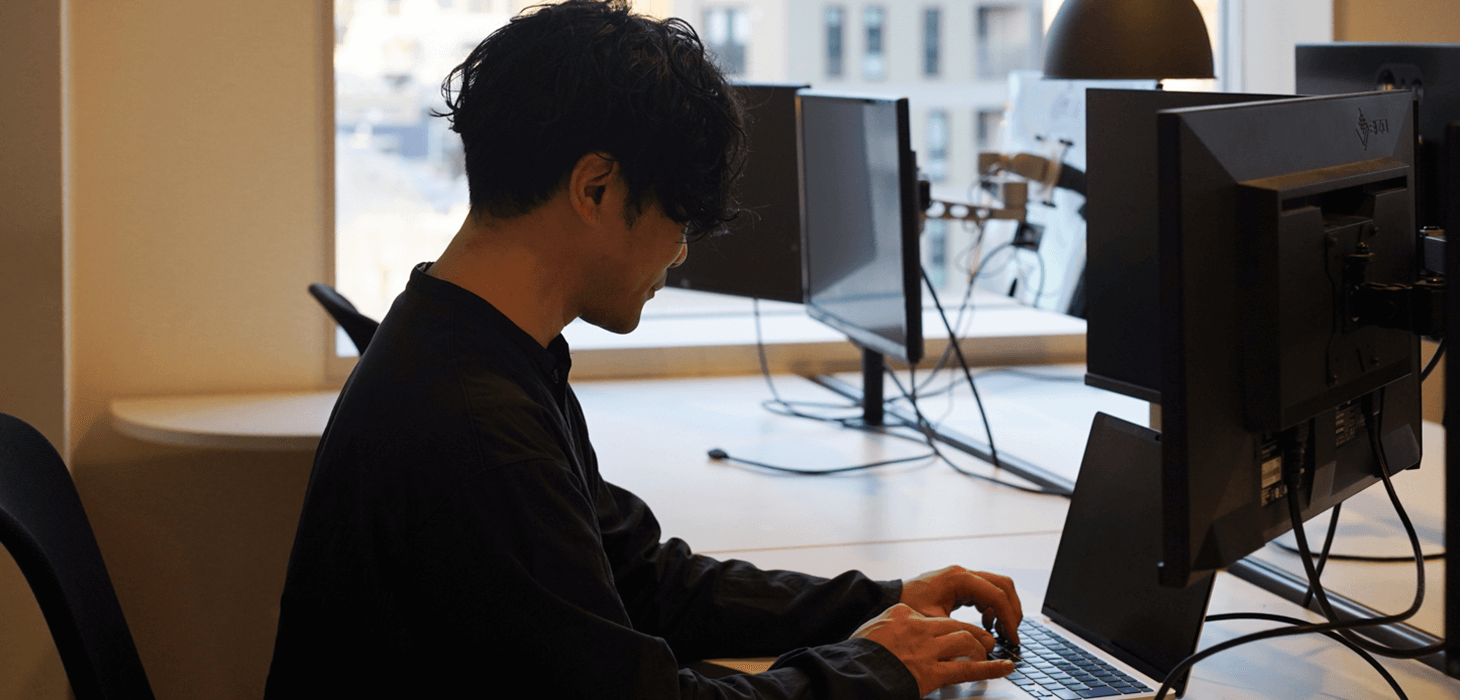
「そもそも」を提案できる機能としてのビジネスデザインチーム
— 2021年には、ビジネスデザインチームを立ち上げられました。どのような背景があったのでしょうか?
さまざまな案件に関わるなかで、「そもそもこのサービスは作らない方がいいのでは?」と感じることが多々ありました。代替案の提案を行う機会もありましたが、やはりご依頼いただいているものは、クライアント内で役員承認を得られているものが大半で、そこと異なる提案を受け入れていただくには、非常に高いハードルがあります。
であれば、「そもそもつくるべきサービスは何か」を一緒にクライアントと模索するところから入れるチームをつくれないかと考え、ビジネスデザインチームを立ち上げることになりました。
— 立ち上げから3年が経ちました。ご自身としては、成果をどのように見ていますか?
計画通りな部分と、そうでない部分があります。ただ、「そもそも作るべきサービスは何か」というフェーズから参画出来ているプロジェクトも増えてきており、モンスターラボのソリューション提供価値を上げることに貢献出来ていると思います。
ビジネスデザインチームに関しては、今後さらにクライアントの内部に深く入り込み、この初期フェーズからモンスターラボならではの独自性を発揮し、価値を提供できるようにしていきたいと考えています。そのために、チームの体制強化、ソリューションの充実、他チームとの連携をさらに深めていきます。
そのうえで僕個人としては、プロデューサー的な立ち位置へと軸を戻していきたいと考えています。もともとチームを立ち上げたのも、クライアント支援においてその機能が必要であり、それが可能なチームをプロデュースしたかったからです。僕に向いているのは、やはりプロデュース業務です。プロデュースを強化することによって、結果的にチームの強化に繋がる機会を創出し、グローバル展開を目指せるプロダクトや事業をクライアントとモンスターラボのメンバーで結託して、生み出していきたいです。
良いプロダクトを、長く愛してもらうために。プロデューサーとして最適な経済合理性を実現ならびに、社会実装したい
— 友部さんが理想とするのは、どのような「プロデュース」なのでしょうか?
大学時代に遡るのですが、過去に小学校の授業をプロデュースするという企画を立ち上げ、僕は体育の授業の1コマをお借りして「キンボール」というスポーツに初めて触れ、学ぶ機会と体験の場をプロデュースしました。スポーツ種目の中には、実は身につけてもらいたい精神や考え方を起点に生まれたものがあり、1人では持ちきれない大きなボールを落とさないようにチームでキャッチすることで競うキンボールにも、「助け合いの精神を身につける」という狙いがあります。そういったコンセプトが忘れ去られ、機械的に経験の場が提供される教育現場に本質を届けるべく、キンボールとの初めての触れ合いの瞬間を劇的なモノにし、一生子供たちの中にコンセプトが宿り続けることを目指したイベントプログラムを作り、提供しました。

このイベントは教師と生徒に感動を起こし、地元新聞からの取材も受け(記事は当時の時事問題に差し代わったか何かでお蔵入りしました…)、一定の成果をあげることが出来ました。
しかし、結局このプログラムが毎年の学校の授業プログラムに採用されることはなく、イベントは1回きりで終わってしまいました。このイベントプログラムを学校予算に組み込んでもらうか、予算を出してくれるスポンサーを見つけることができたら継続できたのに、そこまでプロデュース出来なかった自分の至らなさが原因で途絶えてしまったんです。
この経験から、企画やプロダクトを世に出すときには、その内容も勿論大事なのですが、経済合理性をもってクライアント内ならびに、社会に必然性を以て実装できるようにすることが大切と考えるようになりました。本当に必要なプロダクトであればこそ、それを社会実装するためのお金の儲け方や、時代の流れを汲み取った必然性をどうつくっていくかは、重要なテーマだと言えるのではないでしょうか。
— そんな中で、プロデューサーはどのような存在であるべきだと思いますか?
良いものが生まれてくる裏側には、必ず素晴らしいプロデューサーがいます。その方がステークホルダーと一人ひとり方向性をすり合わせ、筋道を整えているからこそ、良いものを社会実装できているのです。
プロデューサーの腕の見せ所とは、さまざまな文脈を正確に捉えられるか、また、関わる方々全員が損することなく、持続的に社会に利益を還元できる仕組みを用意できるかではないでしょうか。志があれば、その都度変わる文脈の中心に自身の身を置き、さまざまな縁と円をつないで最適解を導きだすことが出来るはずです。
— 今後はどのような動きを考えていますか?友部さんの展望を教えてください。
実は今、国や地方の行政に関心を持っています。最近特に感じるのが、大きく世の中を動かしているのはテクノロジーよりも行政なのではないかということです。EV(電気自動車)やAIなどのテクノロジーが普及するかどうかは、既得権益との戦いを制した上での規制緩和などの後押し如何にかかっているのが現実です。
だからこそ、地政学をどう読み解くかによって事業の成否にも差が出るはず。成功に必要な要素として行政を研究し、地政学を押さえた上でのプロデュースをしていきたいです。最近は、そういった動き方のうまい人やリーダーシップを持っている人がいる地方で、おもしろい動きが起こっています。
この観点で見たとき、とあるライドシェアサービスプラットフォームを提供するスタートアップが大変興味深いです。彼らはプロダクト起点ではなく、地政学起点に動き、展開を目指しているように見受けられます。それゆえの大阪からのサービス展開や現地タクシー会社のM&Aなのだと見ており、今後の事業立ち上げのひとつのモデルケースになるのではないでしょうか。
グローバル展開において、今後ますます地政学観点の理解は必要になるとみており、押さえるところを押さえ、活かせるものは最大限活かしたうえで、支援出来ればと考えています。

Monstarlabで一緒に働きませんか。
UI/UXデザインに関するご相談や、
案件のご依頼はこちら

-
by Monstarlab Design Journal
Monstarlab Design Journal 編集部です。 モンスターラボデザインチームのデザインナレッジとカルチャーを発信していきます。
- Share this article:

 AI時代にも手を動かし続けたい。助言と反響を糧に成長する若手…
AI時代にも手を動かし続けたい。助言と反響を糧に成長する若手…
 個人から組織へ。モノづくりの可能性を広げる、デザイナーの新た…
個人から組織へ。モノづくりの可能性を広げる、デザイナーの新た…
 世界に通用するプロダクトを。諦めを知らないプロデューサーは、…
世界に通用するプロダクトを。諦めを知らないプロデューサーは、…
 自由と制約の狭間で、パズルのように紡ぐUXデザイン。ユーザー…
自由と制約の狭間で、パズルのように紡ぐUXデザイン。ユーザー…
 常に知識を吸収し、手放すことも恐れない。より良いものづくりは…
常に知識を吸収し、手放すことも恐れない。より良いものづくりは…
 「らしさ」を体現するデザインを追求。クリエイティブで人の感情…
「らしさ」を体現するデザインを追求。クリエイティブで人の感情…
 自分の「領域」を、広げ続けていきたい。目指すのは「ユーザーの…
自分の「領域」を、広げ続けていきたい。目指すのは「ユーザーの…
 会話のようにデザインする。問いかけと返答の応酬に感じる可能性…
会話のようにデザインする。問いかけと返答の応酬に感じる可能性…
 「UX」に出会い、もの・ことづくりへの根拠と自信を得た。ビジ…
「UX」に出会い、もの・ことづくりへの根拠と自信を得た。ビジ…
 ミッションは「新しい風」 時代に合わせポジティブに変化する組…
ミッションは「新しい風」 時代に合わせポジティブに変化する組…
Recommended
Overview
×- 社名
- 株式会社A.C.O.
- 設立
- 2000年12月
- 資本金
- 10,000,000円
- 代表者
- 代表取締役 長田 寛司
- 所在地
- 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー6F





 8 suki
8 suki











